【韓国】【韓流新時代】K—POP専門家「JーPOPがヒントに」[媒体](2020/10/26)

「韓流」の強さの秘訣(ひけつ)を探るインタビュー企画の第4弾。今回は、大衆音楽専門家で「K―POPの時代~カセットテープからストリーミングまで」の著者でもある韓国ジョージ・メイソン大学の李奎卓(イ・ギュタク)教授に、K―POPが世界に飛躍した契機や根深い課題など、その光と影について書面で聞いた。【坂部哲生】
■教育ノウハウはジャニーズから
――J—POPと比べたK—POPの強みはどこにあるか。
K—POPはもともと、J—POPの影響を大きく受けている。特に育成制度などはジャニーズ事務所からのノウハウを取り入れたものだ。
ただ現在は、J―POP以上にダンスや歌唱力などパフォーマンスの高さを重要視するのが特徴となっている。このため芸能事務所では、練習生たちに対して体系的な教育を施している。
――日本と韓国でファンが求めるものが違うためか。
日本では、音楽的には未熟であったとしても親切で礼儀正しく、ファンとの交流を大切にするアイドルの人気が高い。ファンは彼らに高い音楽性を期待するよりも「成熟したスターへと成長していくプロセスを共有したい」という願望が強い。
■トータルマネジメントが奏効
――K—POPがビジネスモデルを転換する契機は何だったのか。
2000年代の初め、韓国で大きな人気を誇っていたアイドルたちに対して「音楽的に未熟だ」という批判の声が高まった。追い打ちをかけるように、所属する芸能事務所との契約が、アイドル側にとって一方的に不利な内容になっていることも社会的な問題として注目された。
韓国の芸能事務所は生き残りをかけて、より洗練された体系的な訓練をアイドルの卵たちに施し、彼らを完成した歌手としてデビューさせる「トータルマネジメント(total management)」戦略を取るようになった。アイドルの卵をデビューの企画段階から商品として完全に管理することで、アイドルの海外進出も可能になった。
■過酷な競争など社会問題に
――一方で「芸能事務所の訓練は過酷だ」という話も聞く。デビューまでこぎつけられるのはほんの一握りで、多くの若者は脱落し、その後もきちんとした仕事に就けないケースが多い。
行きすぎた過酷な競争とそれによる脱落者たちの問題は、音楽業界だけでなく韓国社会全般の問題だ。その点では日本も例外ではないと聞いている。何よりも、アイドル歌手たちの行動に対する過度な干渉が問題だろう。
昔と比べれば随分と改善されたが、今でもアイドルにとって不利な契約内容が依然として多く、必要以上に自由が制限されることもある。
――新型コロナウイルス感染症の拡大で、オンラインでのライブ配信が増えている。K—POP業界にどんな影響を与えると考えるか。
K—POPが産業として世界的に成功した要因の一つに、00年代半ば以降、動画配信サイト「ユーチューブ」や会員制交流サイト(SNS)などのメディアを積極的に活用してきた点が挙げられる。オンラインでのライブ配信も以前からの試みの一つであり、コロナ禍の影響でその動きに拍車がかかった。
■ポストBTSを見据えて
――「BTS(防弾少年団)」が所属する芸能事務所「ビッグヒットエンターテインメント」が上場した。ただ、BTSへの依存が懸念され、株価が続落している。
ビッグヒットエンターテインメントのBTSへの依存度が高いのは事実だ。しかし、メンバーの入隊で1年半から2年ほど活動ができなくなる場合に備えて、さまざまな手を打とうとしている。
例えば昨年は、TOMORROW X TOGETHER(TXT)という弟分の男性グループをデビューさせた。人気ガールズグループ「ガールフレンド」の企画会社や男性グループ「セブンティーン」と「ニューイースト」の企画会社も買収し、事業の拡張を図ろうとしている。
過去に比べて兵役の期間も短くなった。多少の空白期があったとしても、会社の将来に致命的な損失をもたらすことはないだろう。
<プロフィル>
李奎卓:
1978年生まれ。韓国ジョージ・メイソン大学教授。大衆音楽の専門家。ソウル大学英語英文学科卒業後、同大大学院で修士号、米ジョージメイソン大学で博士号を、それぞれ取得した。15年から現職。著書に「K—POPの時代」などがある。



 株式会社NNA提供
株式会社NNA提供


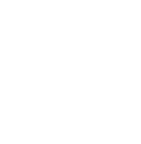


](/img/noimage.jpg)
](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/leaders-online/2020/11/tie_large_638b27ee-fec2-440c-80dc-77dbaf33683a.jpg)